キャッシュレス化:日本の現状と展望
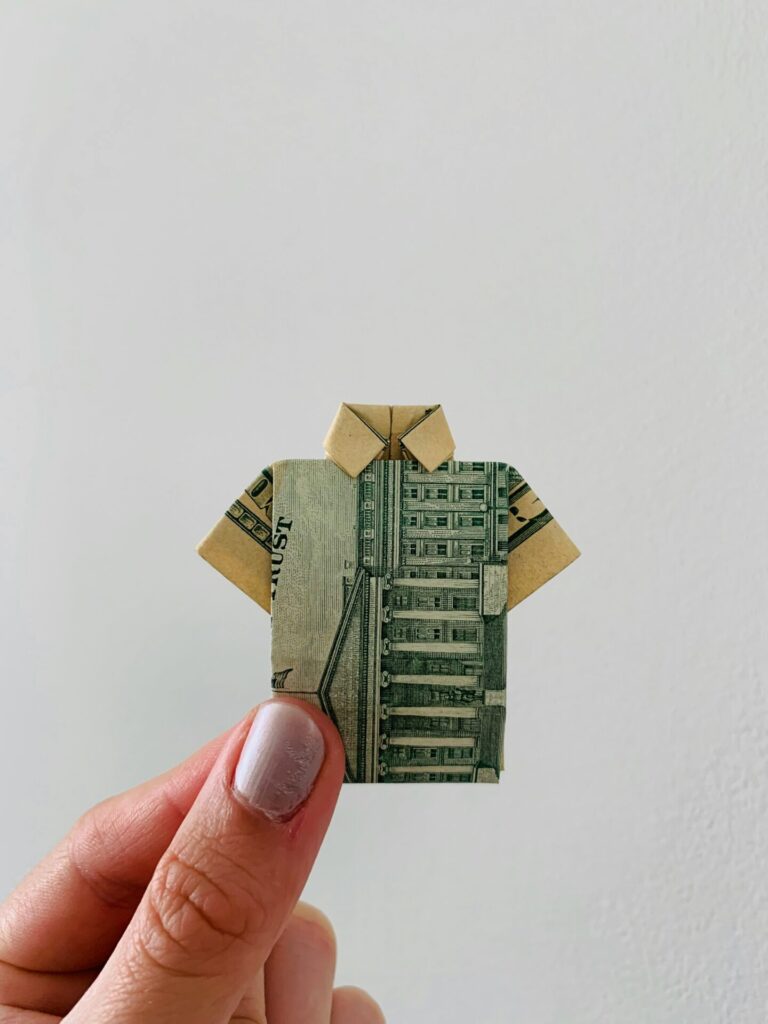
⚫︎日本のキャッシュレス事情
日本では近年キャッシュレス決済の利用が着実に増加しています。経済産業省の発表によれば、2023年のキャッシュレス決済比率は39.3%と過去最高を記録し、政府が掲げた「2025年までに40%」という目標に迫っています 。現金志向が根強い日本ですが、政府主導のポイント還元策や普及キャンペーンも後押しとなり、キャッシュレス化が進んできました。特に新型コロナ禍以降、非接触で支払いができる利便性や衛生面の利点から、スマホ決済などの利用が広がっています。
消費者の動向: 若年層を中心にスマートフォンでの決済が日常化しつつあります。一方、高齢者層では「現金の方が安心」といった声も根強く、セキュリティへの不安からキャッシュレス利用に慎重な傾向も見られます 。それでもポイント還元や割引などのメリットに惹かれて利用を始める人が増えており、現金派だった消費者も徐々にキャッシュレスに移行しています。
主要なキャッシュレス決済サービス: 日本で利用できる主なキャッシュレス手段には以下のようなものがあります。
• クレジットカード: VisaやMastercard、JCBなどのカードブランドによる決済。最も古くから普及しており、高額決済やネット通販で広く利用されています。最近ではカードを専用端末にかざすタッチ決済も増え、少額でもサイン不要で支払えるようになっています。
• QRコード決済(スマホ決済): スマホアプリに表示したバーコード/QRコードを店頭で読み取ってもらう方式です。NTTドコモの「d払い」 やPayPay、楽天ペイ、au PAY、メルペイなど多数のサービスが乱立しましたが、現在は主要サービス間の提携も進み利便性が向上しています。利用者はスマホさえあれば財布を持たずに買い物でき、小規模店舗でも導入が進んでいます。
• 電子マネー(ICカード型決済): 交通系ICのSuicaやPASMO、流通系の楽天Edy、nanaco、WAONなど、プリペイド式でチャージして使う電子マネーも広く普及しています。改札や自動販売機でも使える手軽さから日常生活に浸透し、最近はスマホにカードを登録してモバイル版で使う人も増えています。
政府もキャッシュレス推進に力を入れており、2019年にはキャッシュレス・消費者還元事業を実施し、中小店舗でキャッシュレス決済した消費者にポイント還元を行いました。さらにマイナンバーカードと連動した「マイナポイント」制度など、政策的な後押しも相次いでいます。こうした取組により店舗側の導入も進み、クレジットカード決済端末の普及やQRコード決済の導入が拡大しました。ただ、日本の現金流通の信頼性の高さ(偽札が少ない等)や、加盟店手数料の負担の問題から 、日本のキャッシュレス比率は韓国や中国ほど急激には伸びておらず、今後も緩やかな上昇が見込まれています。

⚫︎世界のキャッシュレス事情
世界に目を向けると、国や地域によってキャッシュレス化の進展度合いは大きく異なります。日本のキャッシュレス比率が約3~4割なのに対し、海外では現金離れがさらに進んだ例もあります 。主要な国・地域の状況を比較してみましょう。
• アメリカ: クレジットカード社会とも言われ、全支払いの5割超がキャッシュレスとされます 。デビットカードも含めカード決済が主流で、小額でもカード払いする文化が根付いています。一方、モバイル決済はApple PayやGoogle Payが利用可能とはいえ、中国ほど圧倒的ではなく、従来のカードインフラにスマホを乗せた形で普及が進んでいます。現金もまだ使われますが、小売店では現金お断りの動きも出始めています。
• 中国: 「現金不要」と言われるほどキャッシュレス化が進んだ社会です。主要都市部では屋台からタクシーまでAlipay(支付宝)やWeChat Pay(微信支付)によるスマホ決済が当たり前になっており、中国国民の8割以上がキャッシュレス決済を利用していると言われます 。銀行のカードやATMより先にモバイル決済が普及したことで、一気に現金離れが進みました。現在では一部店舗で現金が使えないケースすらあり、スマホさえあれば日常生活が送れる環境が整っています。
• インド: 2016年の高額紙幣廃止を契機に、政府主導で急速にキャッシュレス化が進みました 。特にUPI(Unified Payments Interface)というリアルタイム決済プラットフォームの整備により、スマホさえあれば銀行口座間送金や支払いが数秒で完了する仕組みが全国に普及しました。今では露店や個人商店でもQRコードを掲示し、消費者がスマホアプリで送金するのが一般的です。その結果、現金の利用率は大きく低下し、モバイル決済件数は爆発的に増加しています 。2023年時点でUPIによる月間取引件数が数十億件に達するなど、インドは世界有数のキャッシュレス大国へと変貌しつつあります。

⚫︎今後の展望
世界的な潮流としてキャッシュレス化は今後さらに拡大すると見込まれますが、日本がそれに追随する上ではいくつかの課題も指摘されています。
• 高齢者やデジタル弱者への対応: スマホ操作に不慣れな高齢者層など、キャッシュレス決済の利用にハードルを感じる人々へのサポートが必要です。誰もが使いやすいインターフェースや、教育・啓蒙活動を通じた利用促進が課題です。
• 加盟店手数料やインフラコスト: クレジットカード決済の手数料負担が重いことは、中小店舗が導入を渋る一因です 。決済事業者間の競争や政府の支援により、手数料の引き下げや決済端末導入補助などが求められます。
• セキュリティ強化と信頼性: 不正利用や個人情報漏洩への不安から現金を好む消費者もいます。フィッシング詐欺対策や二要素認証の徹底など、安心して利用できる環境づくりが重要です。
こうした課題に対し、政府はキャッシュレス決済の標準化・利便性向上に向けたロードマップを策定し、2025年以降も普及策を継続していく方針です。また、民間でも決済サービスの統合や提携が進み、ユーザーが一つのアプリで複数の決済手段を使えるようになるなど利便性が上がってきています。今後は生体認証(指紋や顔認証)による決済 や、スマートフォン以外のウェアラブルデバイスでの決済、さらには中央銀行デジタル通貨(CBDC)の導入可能性など、新たな技術も視野に入っています。
日本市場の今後の成長見通しとしては、まず政府目標である2025年に40%というキャッシュレス比率は達成が確実視されています 。さらにその先、2030年頃には50%前後、将来的には現金利用が少数派になる水準(80%程度)まで引き上げていく構想もあります。実現に向けては、安全性と利便性を両立させ、誰もが恩恵を享受できるキャッシュレス社会を築くことが求められるでしょう。技術革新と適切な制度・ルール整備を進めることで、2025年以降の日本のキャッシュレス化はより一層加速していくと期待されます。


